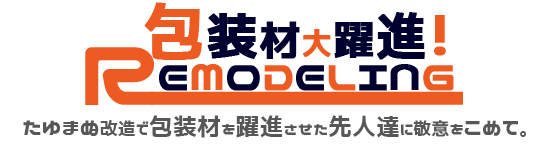包装の簡便化
1957年には、即席で作れるインスタント食品、1967年にはレトルト系の食品、1987年には電子レンジ1つで調理可能な食品というように、食品が進化した背景には、包装の簡便化の進化があります。
コンビニのおにぎりは中身が湿気ってしまわないよう海苔・ご飯・具材が別々に包装されていながら内容物が取り出しやすい開封性を、湿気りやすい食品などには一度開封しても中身が湿気ったり異物が入らないようチャックなどで閉じることができる再封性を、
冷凍食品やレトルト食品などは電子レンジや熱湯に入れてそのまま加熱処理できる耐熱性を、薬を飲む際に重宝されているカプセルやフィルムなどは包装する素材そのものを食べることができる可食性を活用しています。